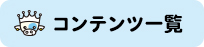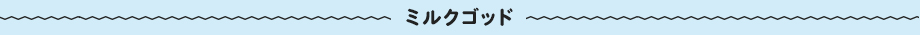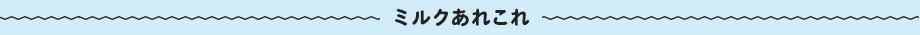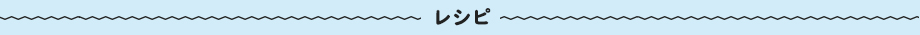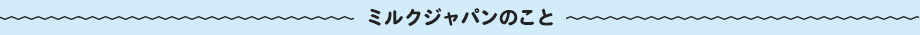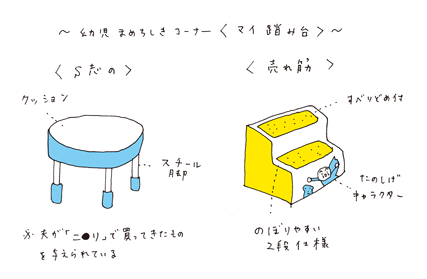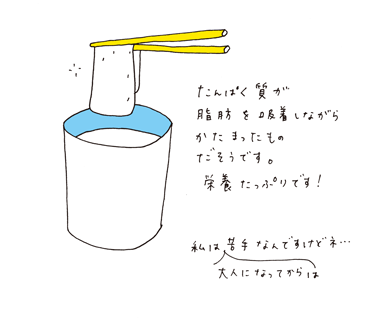おだやかな春風がそよぐ日が増えましたが、
私のまわりでは、大人のインフルエンザが大流行しています。
ウイルスは暖かさにヨワいといわれるけれど、
まだまだもうひと稼ぎ(?)するつもりなのでしょうか……。
月曜日はとっても寒かったので、
ちょっと久しぶりに、夜はホットミルクをつくりました。
いつものように小鍋でくつくつ温めていたら、
わが家のミルティンくんことS志が
彼のマイ踏み台(幼児の必需品)を無言でとなりに置いて、
キッチン台に手をかけてじっと牛乳を見ていました。
なぜでしょうね。
牛乳をわかしている鍋を、じっと眺めてしまうのは。
私もそうだし、S志もそうみたいです。
この疑問から思い出したお話があるので、
今日はまずそれをご紹介します。
私は随筆家の内田百閒(うちだ・ひゃっけん)が大好きです。
気ままで猫好き、借金ばかりしている百閒さんの文章は天然ボケ的なユーモアがあって、声を出して笑ってしまうくらい面白いんですよねえ。
さらにお酒と食べものへのこだわりがとっても強くて、
『御馳走帖』という、食べもののことばっかりまとめた随筆集もあるほどです。
先日、これを読んでいたら、「牛乳」という随筆を発見!
そこには、こんな少年時代のことが書かれていました。
「牛乳屋が来ると家の者が牛乳を沸かす土鍋を出してそれに注いで貰ふのである」
百閒さんは大正〜昭和にかけて活躍した人なので、少年時代といえば明治20〜30年代です。岡山の造り酒屋のひとりっこ。牛乳がとても珍しい時代で、牛乳屋さんが来ると、飼い犬がそばについて離れなかったとも書かれています。
牛乳屋さんは、ひしゃくで量り売りしていて、「最後の一杯は必ずなみなみと溢れさせておまけをする」「地べたに二三滴牛乳を垂らし、犬にもお愛想して帰る」のだそうです。なかなか、気が利いた牛乳屋さんですね。
当時は牛乳を生で飲むということはなく、必ず鍋で沸かしてからでした。
そして、内田少年はそんなとき、いつもそばで煮立ってくるのを眺めていました。
そのようすをこんなふうに書いています。
「初めに牛乳の表面に細かい皺が走ったと思ふと薄皮が張って
土鍋の内側の縁に小さな泡がたまって来る。
どう云ふわけかだかその小さな泡を牛の子だと云って教えられた。
牛の子の泡が縁から次第に真中の方へふえて来て
薄皮の裏側に一ぱいになると、
急に薄皮がふくれ上がって土鍋から溢れさうになる所で
火から下ろす」
牛乳の泡が「牛の子」。
100年の時を超えて百閒さんの家の人に尋ねたい。どう云ふわけ。
でも、牛乳が沸いてくるようすって本当にこんな感じですよね。
むしょうにまた牛乳の鍋を火にかけたくなってきちゃいました。
きのう、鍋を見つめていたS志も、
「ねえ、おしえてあげようか?」と(裏世界の情報屋のごとき)クール顔で、
「おなべのぎゅうにゅうのあぶくはね……
しゃぼんだまなんだよ……
おなべがしゃぼんだましてるんだよ……」
意外とロマンティックなこと言いました。
牛乳を沸かしているようすを眺めていたくなるのは、
ふしぎなことがたくさん起こるからかもしれません。
まっしろな表面に、小さな泡が少しずつ増えてきたり、シワが寄ってきたり。
百閒さんがながながと文章に書きたくなったのも、よくわかる気がします。
「泡が牛の子」発言も、S志みたいに、
何か楽しいことを考えたのかな。
そのふしぎ現象の代表格といえば、温めるとできる、薄皮ですよね!
先日、私の親が私に「あぶら身はガム」と教えていたことを書きましたが、この薄皮も、子どもの頃「ガム」って教わりました。当然、大喜びで薄皮だけ食べてました。私はどれだけガム神話の虜だったんだ。
ちなみにS志の場合は、
「ゼリーができたあー!!」
と言ってはスプーンですくって食べています。
S志にとっては、ホットミルクのいちばんの楽しみだったりして。
随筆にはこの薄皮についても、続きがありまして。
「その皮に滋養があるなどと云ふ事は当時は考へなかった様で、少し冷めて固まりかけたのを箸の先に巻きつけて捨ててしまった」
内田家の家の人は容赦なかった……!(気持ちはわかりますけども)
内田少年にぜひ食べてみてほしかったなあ。でもこの一文からも、少しだけ「食べたかった」気持ちが伝わってくるような気がする。
ちなみに、百閒さんは大人になってからも牛乳好きで、
「朝飯代りには牛乳一合と英字ビスケット一握り、林檎一顆づつ食べる
(中略)もう四五年来この仕来りを変へない」
ということも別の随筆に書いていますが、
この「牛乳」という随筆は、こんな一文で終わります。
「それから四十何年過ぎた今でも矢っ張り毎日牛乳を飲んでいる。
だれかが子供みたいだと云って笑ったが、
さう云はれて見るとそんな気もする」
※『御馳走帖』(中公文庫刊)は、食べもの愛が爆発した随筆が70編あまり収まった楽しい本です。初稿は昭和21年だそうです。